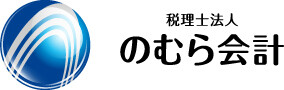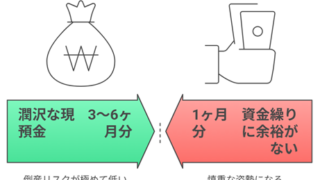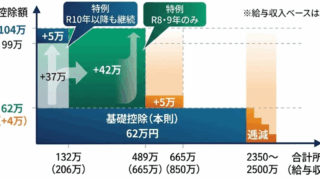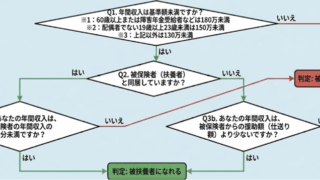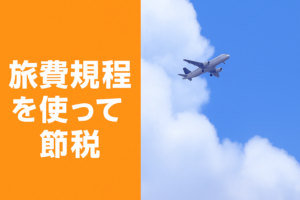個人事業と法人、どちらが有利?法人成り、個人成りの判断基準
石川県金沢市にある税理士法人のむら会計、公認会計士・税理士の野村です。
事業を始める際、多くの方が個人事業主としてスタートします。
しかし、事業が軌道に乗り、利益が増加してくると「法人成り」を検討する場面が出てきます。
個人事業と法人、どちらが有利かを判断するには、さまざまな要素を考慮する必要があります。
この記事では、個人と法人、それぞれのメリット・デメリットを整理し、どちらが有利かを考えます。
現在、個人事業主で「法人成り」を検討している方はもちろん、法人で事業をしているが「個人成り(法人から個人に戻す)」を考えている方にも参考になればと思います。
法人化のメリット
1. 税率を下げられる
個人事業主として事業所得が増加すると、所得税が累進課税によって高額になります。
特に所得が900万円を超えると、その部分には所得税率33%が適用され、これに住民税10%を加えると、合計で43%の負担となります。

一方で、法人化すると、中小企業の場合は所得が800万円までは約25%。800万円超の部分が約35%が適用され、個人にかかる所得税のように、所得が増えれば増えるほど税率が上がる仕組みとは異なる仕組みとなります。
これを利用して、役員報酬を経費として計上できることを活かし、意図的に法人に残る利益を800万円以下に抑えて、残りを役員報酬とすることで、個人・法人トータルでの税負担を大きく抑えることが可能となります。
2. 社会的信用の向上
法人化することで、取引先や金融機関からの信用度が向上します。
特に、一部の企業では「法人でないと取引をしない」と規定しているケースがあり、個人事業主のままではビジネスチャンスを逃すことがあります。
弊社で法人成りをお手伝いするケースでも、取引先からの要請で法人成りするケースも多数事例があります。
3. 節税対策が豊富
法人では役員報酬、退職金、福利厚生費などを経費として計上でき、個人事業主よりも節税の幅が広がります。
特に、以下のような節税策が法人ならではのメリットとして挙げられます。
①旅費規程の活用
役員や従業員の出張費を非課税で支給でき、個人所得を圧縮できます。
②社宅家賃の経費化
社宅として利用する住宅を法人契約とし、家賃を法人の経費に計上可能です。結果、個人側で多くの所得をとる必要がなくなり、個人にかかる税金の削減にも繋がります。
③生命保険の活用
法人名義で生命保険に加入し、保険料を経費処理することで節税が可能です。個人で生命保険に加入するのと比べ、経費処理できる部分が法人だと多いのが特徴となります。また、退職金積立目的も兼ねて生命保険に加入し、多額の退職金を支給すると、所得税だけでなく、社会保険料の削減にも繋がるメリットがあります。
法人化のデメリット
1. 社会保険料の負担増
法人化すると、役員報酬や従業員の給料に対して社会保険料がかかります。
社会保険料は、個人負担が約15%、法人負担が約15%となり、合計で約30%もの負担となります。
法人化すると報酬額に応じて社会保険料が比例的に増加するため、結果として支出が大きくなるケースが多く見られます。
一方、個人事業主の場合、国民健康保険料には上限が設定されているため、所得が増加しても急激に負担が増えることはありません。
「税金」だけを考えれば法人成りが有利なケースでも、「社会保険料」を考慮すると、法人成りしない方が手取りが多いケースもあるため、社会保険料の負担もしっかり検討しましょう。

2. コストと手間がかかる
法人維持には登記費用や税理士費用がかかり、決算書作成や法人税申告、議事録作成などが煩雑です。
管理や手続きが増えるため、事務負担も大きくなります。
さらに、法人には「住民税均等割」という負担が発生します。
たとえ赤字であっても、法人住民税の均等割(最低約7万円)は毎年かかるため、利益が出ない年でも維持コストが発生する点に注意が必要です。
年間所得が数百万円程度であれば、法人成りするメリットが薄く、維持コストが負担となる可能性があります。
事業規模が小さいうちは、個人事業のままでいた方が有利なケースが多いです。
3. 社長個人と法人の分離が厳格化される
法人化すると、法人と個人(社長や役員)の資産や利益を明確に分ける必要があります。
「自分の会社だから好きにしていいだろう」というのが普通の感覚かと思います。
一方で、法律上は会社自体が「法人格」を持ち、個人とは別の存在として扱われます。
そのため、会社の資産や利益を個人が完全に自由には使うことができません。
税務上は、個人と法人の税率差を利用した過度な節税を防止するため、役員報酬は一年に一度金額を決定したら、毎月決めた額を払う必要があります。
例えば「今月は売上が多かったから役員報酬も多めにとろう」とすると、税務上、不利益な取り扱いを受けます。
また、社長の個人的な支払い(生活費や個人旅行代金など)を仮に会社の口座から直接した場合は、「役員貸付金」として処理され、返済義務が発生します。
そして、金融機関の立場からは、「自分が貸したお金を役員が私的に使っている」と捉えて「役員貸付金」があることはマイナス評価として捉えられます。
個人事業であれば「残ったお金はすべて自分のお金」とすることができたのが、法人だと思うようにお金が使えないということで、弊社の顧問先でも個人成りを選択したケースもあります。
もちろん、法的に正しい決議の上であれば、会社の資産や利益を自身のために動かすことはできるのですが、一定の制約があることは理解しておくことが重要となります。
まとめ
目安としては個人事業として、年間所得が500万円を超えるくらいから「税金」だけの観点だと、法人成りが有利なケースも出てきます。
ただし、社会保険料や維持コストも慎重に考慮する必要があります。
特に社会保険料については、所得税や住民税と比べても日本における生涯負担コストの中でも、特に高額となりやすい項目のため、法人成りする前に、必ず社会保険料の試算をすることが大切です。
個人と法人、どちらが有利かは、所得規模やビジネスの性質によっても異なります。
税負担、社会保険料、社会的信用、経費の幅などを総合的に判断し、専門家のアドバイスを受けながら最適な選択をすることが大切です。
弊社として、毎月のように法人成りの支援をしているため、法人化のメリットを享受できるかどうか、具体的なシミュレーションの希望がありましたら、ぜひお問い合わせください。
この記事を書いた人
- 税理士法人のむら会計 代表
-
金沢で60年以上続いている会計事務所、税理士法人のむら会計を運営。
ITの知識・金融機関監査の経験を生かし「関わる人の納得いく決断と安心を誠実にサポートする」ことをミッションに活動している。
【主な保有資格】
公認会計士 登録番号26966
税理士 登録番号125179
【著書・掲載実績・監修】
図解でざっくり会計シリーズ2 退職給付会計の仕組み(中央経済社)
賢い節税で会社を強くする方法教えます(月刊経理ウーマン 16年10月号)
失敗しない「税理士」選びーここがポイントだ!!(月刊経理ウーマン 18年8月号)
決算期を過ぎてもできる節税策ー4つの着眼点ー(月刊経理ウーマン 20年5月号)
社会保険料の会社負担を減らすための、アノ手コノ手を教えます(月刊経理ウーマン 23年9月号)
小規模企業共済のメリット&デメリット(月刊経理ウーマン 24年2月号)
ソニーGなど「賞与の給与化」で手取り増 社会保険料の負担減り一石二鳥(日経ビジネス25年11月10日号)
最近の記事
 経営ワンポイント2026年2月2日銀行から『ぜひ貸したい』と言われる会社に!決算書でチェックされる3つの重要指標
経営ワンポイント2026年2月2日銀行から『ぜひ貸したい』と言われる会社に!決算書でチェックされる3つの重要指標 個人の節税2025年12月23日中小企業向け:令和8年度税制改正大綱のポイント解説
個人の節税2025年12月23日中小企業向け:令和8年度税制改正大綱のポイント解説 経営ワンポイント2025年12月2日社会保険「130万円の壁」の新ルール!2026年4月スタート
経営ワンポイント2025年12月2日社会保険「130万円の壁」の新ルール!2026年4月スタート 経営ワンポイント2025年11月4日石川県賃上げ環境整備助成金 ~先に設備投資していても事後的に適用可能!~
経営ワンポイント2025年11月4日石川県賃上げ環境整備助成金 ~先に設備投資していても事後的に適用可能!~

無料相談のお問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください